小さい頃から祖父に連れられ釣りをやっていた。
中学1年生の頃に三兄に誘われ、はじめたブラックバス釣りにはまり、高校生まではバス釣りがメインだった。
これが大学生になると、他にもいろいろ楽しいことができて、釣りにはいかなくなる。年2、3回ぐらい、実家のある栃木の野池に帰省して、バスやブルーギルを釣ったり、管理釣り場でトラウトをやる程度であったと思う。
大学生で釣りから離れてしまう。
これはよくあるパターンだと思う。学生時代はいろんな魅力があるから。
一種の大学デビューの反動なのかもしれない。
それまで興味があってのめりこんでいたことが、まったく目に入らないときがあるわけだ。
わたしの場合、それほど裕福な家でもなかったので、学費を稼ぐ必要があり最盛期は週6でバイトをしていた。大学1年の頃から20連勤ぐらいしていたこともあったような。
それで講義をおろそかにする。これも典型的な日本の大学生のパターンだと思う。
真鶴へ
そんなバイト過密生活から、どうやって釣りという趣味に戻ってきたか。
思い返すとこれは、東伊豆のゴロタ場でムラソイを釣ってからじゃないかなと思う。
Googleフォトをさかのぼってたら、2015年の正月4日に何をおもったのか、わたしは伊豆方面にバイクで旅にでたらしい。らしいというか、まー写真にきっちり残っているので、旅にでた。

当時、アングラーズリパブリック(現パームス)のバス用パックロッドをもっていて、それに旧型のレブロス(まだボディがシルバー)や、ワームやらを持参してまずは真鶴にむかった。
三ツ石という地名は真鶴半島の突端のことなのだが、そこでわたしは糸を垂らす。カサゴだったり、ムラソイがいるんじゃないだろうかという狙いだったと思う。

三ツ石の穴釣り。ちゃんとやれば釣れたであろう
熱海港は不毛地帯
そしてなんとなく不完全燃焼感があったんだろう。熱海まで走っている。熱海港のフェリーターミナルでメバルを釣ろうとしたら、これが一向に釣れない。
イソメをつけてウキ釣りをやっている人がいたが釣れないという。だいたい1月自体がメバルを釣りやすいかというとそうでもないのと、釣り方自体が適当で、タックルだってバス用なので釣りにくかったんだろう。たしかPEラインをジグヘッドに直結していたような。

魚体自体は独特の照りがあってきれいだ
ようやく釣れたのはオオスジイシモチだった。名前はなんだかすごいが、要はネンブツダイの仲間なので、釣り師からすると堤防ヒエラルキーの最底辺に属している魚だ。
とはいえ、魚のあたりがあったのはうれしかった。

熱海は、今ほど再興してなくて、昼間歩くと寂れ感に満ちていた。
これが夜になって港から街のあかりをみると、なんともきれいで、なんとなく、もはや若くはない夜の女性が化粧をしているような感があった。遠目でみると美しいものというものは世の中にたしかに存在している。

今と比べると防寒装備がチープ過ぎたのでこの表情
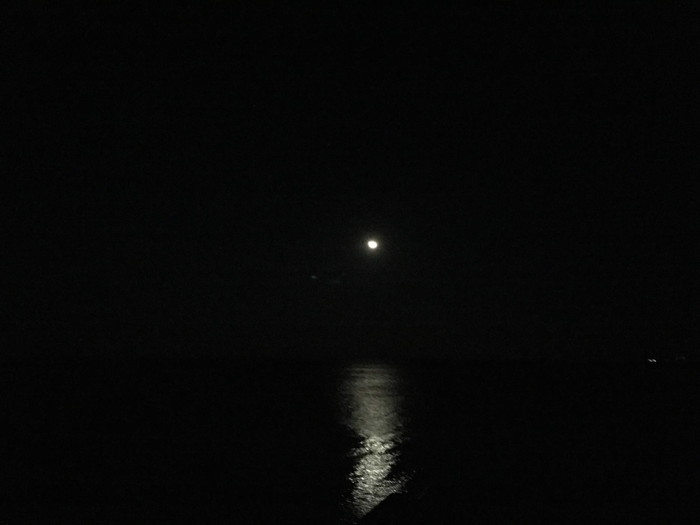
熱海で釣りをおえて、たしか熱海の東急インに宿泊。
翌朝、東京に引き返すかと思いきや、わたしはさらに西へ走った。
男にはこういうときがある。
なんとなく遠くまでいきたい。
女じゃないからわからないけれど、女にもあるのかもしれない。
とにかくもっと遠くまで行ってみたい。そうなるとどこか、一応ゴールを決めたい。
それが城ケ崎だった。
地の果て、城ケ崎

城ケ崎、そこは大地の果て
城ケ崎にいったことがある人はわかるが、断崖絶壁でなんとなく地の果て感がある。その手の最果て感を味わいたいと思っていたのと、磯釣りのメッカであると知っていたからかもしれない。
が、パックロッドで勝負できるのか。
今だったら勝手もわかるので、やる前にこりゃ無理だなとおもって、素直に真鶴伊東間にあるゴロタ場で釣りをする。だけど、当時はよくわかっていなかったのでとにかく城ケ崎まで走ったわけだ。
知らないことが行動につながることもある。
釣りもいつのまにか初心者を卒業していろいろとみえてくる。過度の謙譲で「初心者です!」みたいに、いつまでもふるまうのはなんだか性に合わない。
たどり着いたのは、いがいが根駐車場というところ。そこにバイクをとめて、数分歩くと本格的な磯に出る。尖った根がいくつか続いているので「いがいが根」というのだろう。

こんな道を歩く。スニーカーであるく道じゃない

落ちたら死ぬぞ


そこかしこで磯釣り師が陣地を構築
当時はその危険性もわかっていなかったので、ライフジャケットもつけず、岸壁で釣りをしようとする。
高さは10m以上はあったように記憶しているが、落ちたらまず這い上がれないだろうし、傾斜している岸壁に頭でも打ったら、死んでもおかしくない。
まわりをみると5mぐらいの磯竿をつかって釣りをしている磯釣り師がちらほら見える。今思えば、メジナやら石鯛を釣っていたのだろう。冬場だからブダイを釣っていた人も混じっていたのかも。
そんな絶壁エリアで、6.6フィートぐらいの竿でジグヘッドにワームをつけて投げ込むわたし。今だったらこいつはバカと違うかと思ってしまうかもしれない。
が、わたしもそれほど馬鹿でもないので、だいたい2分ぐらいで、あ、これは場違いってやつだよなと、その場を離れた。青く潮が打ち付ける岸壁から、なにかの拍子に落ちて死ぬイメージが濃くなってきたのも事実だ。
ゴロタ浜、そこはムラソイの巣
いがいが根の東側へすこし歩くと、ゴロタ浜が広がっている。
ここだったらなんとか釣りができそうだな。そうおもって、ブラーにオキアミを刺して投げてみる。水深は浅い。強めの波が寄せてくるので、ボトムをとってブラーを操作すると速攻で根がかる。ラインがPE直結なので、ロストする。
今思うと、相当無駄な釣りをしていた。釣りはジャンルが変わると、ゼロリセットはされないまでも、レベル3ぐらいからスタートすることになる。
この時点で、なんだかここには何もいないのかもなと思って、回収しようとブラーを巻き上げると、何かがバイト。引きは強くない。
・・・
ドロメだった。

当時は名前がわからないかった。不思議なもので、小物のハゼでもアタリがでると、釣り人の士気はすこし回復する。
なにかいるかもとブラーを投げ続けてみる。
すると、岩陰からすごいスピードで発射された「砲弾のような黒い影」が夜光白のブラーに食いつく。
不意のアタリと、その重さ。
興奮して鼻息が荒くなる。
こ・れ・は!
そう、ムラソイである。

人生ではじめて釣ったムラソイは20cmぐらいだったと思う。
そこからジグヘッド+オキアミなどに変えてみて、方々にキャストすると、ムラソイがぽんぽんと釣れた。最大サイズは25cm弱。

今思うと、たいしたことがないサイズだなと思うのだが、当時は久しぶりに釣った魚で、引きも強かったのでかなり大きく見えた。
人間、不思議なもので魚のサイズにも慣れというものがある。
たとえばメバル。釣りをはじめたころは25cm程度でも、物凄く大きく感じたのに、やがて経験が増えると、そこそこの良型サイズだなと思いはじめる。
基準ができる。
そういうことなんだろう。
それに、釣り師の場合、誰かに伝える時に自分のレベルを舐められないように、無意識に自分の釣果を卑下する感覚もあったりする。
話を戻すと、ムラソイは全部で10尾弱程度釣れた。
潮の干満についてもあまり知らなかった当時の自分にしては十分な釣果だった。持ち帰る道具も持ち帰ることも考えてなかったのですべてリリース。
そのまま、アドレナリンが残っているのか、言い知れぬ高揚感をもって伊東まで引き返して、そこで温泉に入った。
その後、港の堤防で野宿をしたような気もするししなかったような気もする。
そのアタリが再度、釣欲に火をつけた
このムラソイとの出会いは、なんらか自分の釣欲に再度火をつけたららしく、同月末にもう1度東伊豆を訪れている。これは伊東あたりのゴロタ浜だった。
その後も、もっと近場でムラソイが釣れるのではないかと、城ヶ島を訪れたり。


スラッゴーのバブルピンク。知る人ぞ知るムラソイキラー

城ヶ島でもムラソイはよく釣れた。オキアミを使っても釣れるが、ワームで釣るのが手も汚れないし、針持もいいと思い始めた。ムラソイであれば、かけそこねた個体じゃなければ、エサはなくても釣れる。
このムラソイなのだが、見た目が可愛いので、一度も持ち帰らなかった。あまり釣って料理する習慣がなかったというのもある。
一度火のついた釣欲は、その後、多摩川のテナガエビ・ナマズ・シーバス釣りあたりに延焼していき、その後に堤防釣りをもっとやるようになり、手漕ぎボートやら釣り船の世界にどっぷりはまっていくことになった。
そして、いままで何人もの大人や子供を釣りの世界へ巻きこんできた。
当人たちにとって、それがよかったのかどうかはわからないけれど、相当数釣り人の増加に寄与してきた感はある。
最近はおかっぱりの釣りをあまりやっていないものの、やはり原点ということもあり、もうすこしやっていきたいと思っている。
あのときの城ケ崎のムラソイ。
浅場で、岩の割れ目から弾丸のように飛び出してくる黒い影。
そして、ズン!とくる、あのアタリ。
釣り人にとって、「アタリ」というものは、一度味わうと二度と忘れることができない興奮なのだと思う。
今でも目を閉じると、いろんなアタリがよみがえってくる・・・。
関連記事


